セネガルニューズレター No.2 2002/02/25
 |
| セネガル |
| Contents |
| セネガルの音楽 |
| セネガルの本 |
| セネガルの手工芸 |
| インターネット |
| 世界遺産 |
| ゴレ島 |
| サンルイ |
| D´accord Dakar! |
| Senegal Link |
| セネガル生活情報 |
| タンザニアのページ |
| マダガスカルのページ |
| アフリカのとんぼ玉ミュージアム |
| アフリカのトンボ玉ミュージアム(ブログ) |
| 世界遺産Facebookページ |
 Paris - Dakar Rarry
Paris - Dakar Rarry
日本人の中には「セネガルってどこだ?」という人は多いかと思いますが、有名なパリ-ダカールラリー(パリダカ)の終点がダカールだということは聞いたことがあるかと思います。ここがセネガルの首都です。 パリダカ・ラリーはセネガルにとっても一年のうちの一台イベントで、特に最終ステージはダカールからさほど遠くないラック・ローズで行われますから、観光客や地元の見物人も多く詰め掛けます。ちなみにラック・ローズはピンク色の湖という意味で、塩分濃度が高いため水がピンク色に見えるのでこの名があります。
さて1月13日に行われた最終ステージの見物には、ダカール在住の日本人も多くの人たちが自家用車や、あるいは貸切バスなどを仕立てて見物に出かけました。僕は協力隊員が仕立てたバスに便乗して出かけました。バスは2台あったのですが、なんだかみんな慌てて白いバスの方に乗り込みます。ぼんやりしていた僕は青い方に乗ったのですが、青い方には窓ガラスが入っていませんでした…。
見物はラック・ローズのすぐ横にある砂丘地帯で行うのですが、炎天下予定時刻を過ぎても待てど暮らせどなかなかレースカーは見えてきません。砂の上に座り込み、同行の人たちと話していると、ふと脇に置いたリュックのチャックが半開きになっているのに気がつきました。あらかじめこうした人ごみにはすりが多い、と聞いていましたからすぐにピンと来て、脇に座っていたセネガル人のお兄ちゃんのひざを小突いてやると、慌てて立ち上がって姿を消しました。油断大敵。
さてそうこうしているうちに、ヘリコプターの爆音が近づいてきました。そうです、空からレースを撮影している取材陣のヘリです。まず姿をあらわしたのはオートバイの一団です。先頭の方のグループは猛スピードで駆け抜けて行くので、写真をとろうにもなかなかうまく行きません。しかし後ろの方のグループになると、観客の前で道を間違えたり、エンストを起こして修理をはじめたりと、結構のんびりしているように見えます。無論やっている人たちは真剣なんでしょうけど。

続いてやってきたのがメインイベント、4輪駆動車を中心とする4輪車部門です。ものすごい音と共に最初にやってきたのは三菱パジェロ3台。大接戦です。結局優勝したのは日本人の増岡浩、2位は昨年女性として初めて優勝したユタ・クラインシュミット、3位は有名な篠塚建次郎でした。上の写真がゴール間近、並んで走っていく先頭の3台です。増岡さんは昨年最終日にレース妨害で順位を落とし、優勝を逃したそうで、今年の優勝は喜びもひとしお、ゴールした後涙を見せていました。
 さてこうした三菱パジェロ組のほかに、順位は低くても僕らにはお目当ての選手もいました。その一人がかつてはF1レースに出場していた片山右京です。僕らは本来関係者以外立ち入り禁止と思われるゴールに、何食わぬ顔をして入り込み、レースを終えた選手たちに会うことができました。右京さんは思ったより小柄で、同行の女性たちの評判では、右京さんのナビゲーターをやっていた男性の方がかっこいい、とのことでした。まあ僕にはどうでもよいことですが。下の写真左側が右京さんです。
さてこうした三菱パジェロ組のほかに、順位は低くても僕らにはお目当ての選手もいました。その一人がかつてはF1レースに出場していた片山右京です。僕らは本来関係者以外立ち入り禁止と思われるゴールに、何食わぬ顔をして入り込み、レースを終えた選手たちに会うことができました。右京さんは思ったより小柄で、同行の女性たちの評判では、右京さんのナビゲーターをやっていた男性の方がかっこいい、とのことでした。まあ僕にはどうでもよいことですが。下の写真左側が右京さんです。
Pause Cafe
Pause Cafeというのは、フランス語でコーヒー・ブレークのことです。僕らの職場で朝10時にお茶の時間を設けました。セネガルでは習慣としてなのか、お昼ご飯の時間が遅めで、僕らの職場では午後1時半に食べるのが普通です。勤務が始まるのが本当は8時だそうですが、実質的には8時半になっています。このため午前中の時間がかなり長いのでその中間に設定したわけです。
しかしコーヒーの時間を設けたのは、お腹がへって昼までもたないからではありません。それだけなら自分のデスクでお菓子でもつまめばよいわけです。セネガルも職場の形式は欧米式になっており、職員はそれぞれが小部屋に分散しています。部屋が十分にありませんから数人で共用してはいますが、暑い国でクーラーを入れている季節が長いせいか、すべての部屋が入り口のドアを閉めて仕事をしています。
こうなると誰が出勤してきているのか、どこで何をしているのかさっぱりわかりません。同じ部屋にいる人とは声を交わしてもそれ以外の人と接する時間が非常に短くなってしまいます。また人間関係が必ずしもスムーズとは限りませんから、気の合わない同士が同じ部屋にずっといたら息も詰まります。そこでコミュニケーションと息抜きを行う場を設けようとコーヒーブレークの時間を作ったわけです。
実は日本人の間で相談していたのですが、セネガル人スタッフの一人であるジョップさんがまったく同じアイデアを持って僕らのところに提案をしてきました。「やっぱり誰でも同じようなことを思っていたんだなあ」とすぐにプロジェクト・マネージャー(セネガル側のプロジェクト代表)のサムラ氏に相談し、コーヒー・ブレークが実現しました。
ところがここでまた問題が持ち上がりました。「コーヒー代は誰が出すの?」という点です。とりあえずのスタートとして僕がポケットからいくらか出し、初日はコーヒー・ブレークを提案したジョップさんが「妻の手作りです」とケーキを持ってきてくれましたが、はて、これをどうやって維持していくのか? 当初はドライバーや秘書さんなども含めて一律お茶代として月に200円程度、と考えていたのですが、参加者が激減してしまいました。どうも「なんで給料の安い俺たちも同額出すの?」そしてさらには「こういうのはパトロンが出してくれるんじゃないの?」という意識が強いようなのです。パトロンというのは、ここでは雇用主のことです。結局給料が安い人たちは任意になりました。 こんな些細なことでもこちらの人の意識とかがうかがえて面白いのですが、さて今後お茶代の集金は本当にできるのでしょうか?!
アフリカ・カップ
これを書いている2月、どうやらアメリカではソルトレーク・冬季オリンピックが行われているようです。インターネットで日本語のニュースなどを見ると、確かに記事が出ているのですが、セネガルではほとんど話題にすらのぼりません。無論雪や氷と無縁のセネガルが選手を送っているわけでもないし、今後も送る予定もないことでしょう。途上国の選手も陸上競技などで活躍している夏のオリンピックとは異なり、冬季オリンピックがいかに北の国々(多くは先進国)のものであるかが良くわかりました。
さて冬季オリンピックに先立って、セネガルの隣国マリで行われていたアフリカのスポーツの一大イベントが、サッカーのアフリカ・カップです。アフリカのチームは日本にはなじみが薄いですが、例えばカメルーンはオリンピックでも優勝していますし、ワールド・カップでもアジアの国が一勝もしていないのに比べると、アフリカの方が実力もあり、層も厚いと言えると思います。 アフリカの強豪と言えば筆頭はカメルーンでしょうが、その他にもナイジェリアや、南アフリカなどが有名でしょうか。
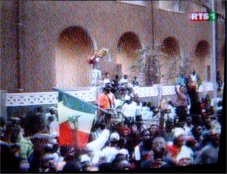 セネガルはと言えば、今まで決勝リーグにも残ったことがなかったそうで、まあどちらかと言えば弱小チームだったのかもしれません。
ところが今年はワールド・カップ初出場も決めていますし、なんとアフリカ・カップでも決勝に進出、強豪カメルーンにはPK合戦の末に惜しくも敗れましたが、堂々の2位に輝いてしまいました。
セネガルはと言えば、今まで決勝リーグにも残ったことがなかったそうで、まあどちらかと言えば弱小チームだったのかもしれません。
ところが今年はワールド・カップ初出場も決めていますし、なんとアフリカ・カップでも決勝に進出、強豪カメルーンにはPK合戦の末に惜しくも敗れましたが、堂々の2位に輝いてしまいました。
フランス人の監督を雇用し、ヨーロッパでプレーしている選手を呼び戻してチーム編成したのが功を奏したと言われていますが、それにしても大躍進には違いありません。 セネガルが勝利を収めた後は、町には若者たちが繰り出し乱痴気騒ぎ。そしてチームが準優勝を決めて帰って来た日は町はお祭り騒ぎで夜中まで歓声が絶えませんでした。下の写真はテレビに写った群集の様子です。
タバスキの祭り
セネガルやその周辺の国々では、人々の多くがイスラム教を信じています。イスラム教にはいくつかの大きなお祭りがありますが、その中でも重要なのがこのあたりではタバスキと呼ばれるお祭りで、この日のために何日も前から準備をしたり、また家族と過ごすためにふるさとに帰ったりします。そうしたところはちょっと日本のお正月の風景に似ている、と言えるでしょうか。(イスラム教の新年は別にあります)今年は2月23日がこのあたりでのタバスキの日でした。
タバスキのお祭りの起源はモハメッドがイスラム教を起こす以前、数千年も前にあります。イスラム教、ユダヤ教、キリスト教共通のものである旧約聖書に、アブラハムが神様に信仰心をためされ、自分の息子をいけにえにささげようとする話があります。実際にはアブラハムが一番大切な息子をささげようとするのを確かめた神様は、息子のかわりに羊をささげるようアブラハムに告げたのですが、このため今では羊をささげるお祭りになっているのです。
タバスキが近づくと、まちの周辺はいたるところ羊だらけ。あっちでもメエメエ、こっちでもメエメエ。羊たちはセネガルだけではまかないきれず、ニジェールやマリなど、周辺の国からも輸入されるのだそうです。中には福引の商品として羊を出しているスーパーマーケットまでありました。お金のない人たちはあちらこちらから借金したり、給料の前借をしたりして羊を買います。 羊ならどんなものでも良い、というわけにはいきません。なにしろアブラハムの大切な息子のかわりにする羊ですから、自分に買える最上のものを準備しなくてはいけません。とは言ってもお金持ちもいれば貧乏な人もいますから、羊の値段も一頭5千円くらいから、5万円くらいまでと幅があるそうです。
 さてタバスキの朝、各家では家の主人がアラーの神にお祈りをささげてから、羊ののどをナイフで切って殺します(余談ですが、フランス語には喉を切るという意味のegorgerという単語がちゃんとあります)。羊はその場で解体され、神様に感謝しながら焼いてみんなで食べてしまいます。僕がおじゃましたプロジェクト・マネージャーのサムラさんのお宅では、サムラさんが喉を切った羊を男の人たちが解体し、女の人たちが肉を炭火で焼いていました。イスラム教のお祭りですからお酒は出ず、飲み物はジュースです。
頭の部分はごろんとおけの中に入っていましたが、これももちろん食べられてしまいます。特に目玉や頬の肉はおいしいとか。日本の魚となんだか似ています。僕はこういうのはどちらかと言えば苦手なので、内心出てこなくて良かった、と思っていました。
さてタバスキの朝、各家では家の主人がアラーの神にお祈りをささげてから、羊ののどをナイフで切って殺します(余談ですが、フランス語には喉を切るという意味のegorgerという単語がちゃんとあります)。羊はその場で解体され、神様に感謝しながら焼いてみんなで食べてしまいます。僕がおじゃましたプロジェクト・マネージャーのサムラさんのお宅では、サムラさんが喉を切った羊を男の人たちが解体し、女の人たちが肉を炭火で焼いていました。イスラム教のお祭りですからお酒は出ず、飲み物はジュースです。
頭の部分はごろんとおけの中に入っていましたが、これももちろん食べられてしまいます。特に目玉や頬の肉はおいしいとか。日本の魚となんだか似ています。僕はこういうのはどちらかと言えば苦手なので、内心出てこなくて良かった、と思っていました。
(2015年はひつじ年で、ヒツジの写真やイラストを年賀状に使う人が多いと思いますが、この写真はちょっと…使えませんね。ヒツジのイラストを探して辿り着かれた方ごめんなさい。)
ただ殺した羊に関してもいろいろと約束事があります。まずあまった肉を冷蔵庫などで保管してはいけません。使い切ってしまわなくてはいけないのです。昔のしきたりだと、羊の肉は三つに分け、そのうちの一つは自分の家族で食べ、二つ目は貧乏で羊が買えない人に分け、三つ目はイスラム教徒ではない人たちに分けるのだそうです。そして自分のところで取り込んでしまわないように、冷蔵庫にしまってはいけない、という約束事ができたそうです。
西アフリカではヤギよりも羊が重要な役割を果たしているようですが、以前いたケニアやタンザニアでは、イスラム教徒がいるにもかかわらず、羊を屠るタバスキの祭りはあまり盛んではなかったように思います。僕がよく行っていたイスラム教徒の村でも、羊はほとんどおらず、ヤギばかりでした。その辺りを見ると、どうもイスラム教以前の習慣や風土(ヤギを飼うか羊を飼うか)が現在の風習にもかなり影響をしているのではないか、という気がします。
1月の半ばにホテルを出てアパートに移りました。広くて静かなアパートですが、クーラーがなかったころ暑さを避けるためか、天井がやたら高くなっています。電球がよく切れるのですが、自分では手が届かなくて、いちいちアパートの管理人に連絡しなくてはなりません。ただここも4月には出て、別のところに移る予定です。
自動車は、フランス製のプジョーを注文したのですが、フランスからの船が到着してみると、なんと、僕の注文したのとは違う車が積み込まれてしまっていたことがわかりました。仕方がないのでこの車を買うことにしましたが、注文したのとは違うものを買うのは実はケニアに続いて2度目です。途上国と言えども、それほどよくある話ではないはずなのですが。